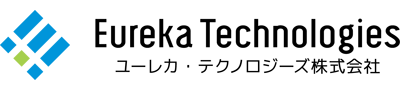研究室やバイオバンク、製造施設における、検体の識別は全体の効率や生産性、そして何よりも確実な追跡性を担保するための最重要なファクターです。検体識別には、幾つかのアプローチがありますが、何がもっとも適した手段なのか正しくアセスメントした上で採用するべきです。安易に選択された識別方法で超低温保管された検体は、容易に取り出すことができず、また識別方法を再選定することには大変な労力と損失を伴うからです。
この記事では、大きく3つに大別された検体識別手段のメリットとデメリット、その方向性をご紹介します。

検体識別ラベル

ラベルを用いた識別は、検体管理のゴールドスタンダードと言えるでしょう。多くの場合、管理は小スケールから始まることが多く、初期投資が少なくて済む識別ラベルはリーズナブルな選択肢です。特殊な投資は必要なく、ラベルプリンター(熱転写 or 感熱)とバーコードリーダーがあれば、環境は整います。
メリット
現在では、超低温環境のみならず、薬品・有機溶媒耐性やオートクレーブ耐性、凍結面の貼り付けや剥離証明など、様々な機能性ラベルがあり、運用に即した選択が柔軟にできるのもメリットです。
また、PCRチューブやクライオチューブのような小型容器から、フリーズボックス、IVFストロー、病理検体、金属ラック、各種ボトルなど、対象容器の形状やサイズに適したラベルの選択肢が豊富にあります。

デメリット
研究現場で用いられるサンプルは、相互汚染や感染、超低温サンプルからの低温やけどを防止するため、プラスチック手袋を装着した状態での操作が求められます。手袋を装着した状態でのラベル貼付けは、非常にストレスのある作業で、貼り付けミスによるラベル再発行が必要なケースもあります。
また、手順をしっかり管理しておかないと、ラベルの貼り間違いや取り違えが起きるリスクもあります。
解決策
近年、こういった問題を解決するために自動ラベリングシステムが普及しつつあります。この装置は、ラベルの印刷と対象容器への貼付処理を同時に行えるもので、多くのサンプルを扱う検査会社や、自身の試薬・検査キットを製品としてラベリングしたい、というニーズに適しています。
他にも、チューブトップに貼り付けにくい円形ラベルを手早く確実に処理できるPikaTAGや、ラベル台紙が分離することでプラスチック手袋にくっつきにくい、SimPEELテクノロジーラベルなどの便利ツールもあります。

二次元バーコード付チューブ

二次元バーコード付チューブは、ストレージ用チューブなどとも呼ばれる、検体管理のために生み出されたチューブです。SBS規格と呼ばれるマイクロプレートフォーマットのチューブラックに、高密度にチューブが積載できることが特徴です。チューブの容量に応じて、SBS規格ラックのチューブ本数は、96本(0.3~1.4ml程度)、48本(1.5~4ml程度)、24本(5ml~10ml)といったカテゴリに大別されます。
メリット
チューブの底面(加えて側面の場合もある)には、二次元バーコードが刻印されており、ラック装填状態で、専用のラックスキャナーを使えば、一度にすべてのチューブの情報とラック内の位置情報を取得できます。一度に多くの検体の入庫や出庫をしなくてはならない場合、短時間に確実に検体識別ができます。
二次元バーコードは製造元で一貫管理されたIDとなってており、原則として市場に同一のIDは存在しないため、サンプルを一意に特定できます。

SBS規格は、研究現場のデファクトスタンダードであり、96本チューブの場合、ラックのフットプリント、チューブ間のピッチは96ウェルマイクロプレートと同一です。従って8チャンネルピペットや、自動分注装置を用いたアッセイに非常に親和性があります。血液からの血清・血漿などの成分分画処理、PCRや次世代シーケンシング(NGS)処理にシームレスに展開することができるため、大規模な検査やスクリーニングを行う現場向きといえます。
SBS規格:ANSI(American National Standards Institute)で定められたマイクロプレートのサイズ規格

ストレージ用チューブを使った検体管理では、規格化された検体ハンドリングが可能となるため、すべての入出庫操作を自動で行う自動化倉庫で運用することが可能です。その多くは非常に高価ではありますが、確実な入出庫と監査証跡を残すことができるため、堅牢なバンキングシステムには欠かせない要素となっています。

デメリット
ストレージ用チューブは、いかに高密度に検体を保管・管理するかという観点で設計されたものです。特に96本チューブの場合チューブの直径は8mm程度と非常に小さく、キャップを手作業で開閉することには適していません。近年、扱いやすいアウターキャップチューブが普及しつつありますが、効率よく確実にキャップの開閉をするためには、自動デキャッパーなどの装置を利用する必要があり、投資の増大につながります。
また、チューブ固有の二次元バーコードは、チューブ製造元が発行したID(チューブID)であるため、ユーザーが管理したい検体IDと相関させるため、データ上で紐づける必要があります。識別ラベルのように、一見してそのサンプルの情報を識別・判別することはできず、検体管理ソフトウェアなどを通じ、チューブIDを元に検体IDを問い合わせる手続きが必要となります。
近年、チューブ容量は0.3~10mlと幅広いレンジを選択できるようになってきています。しかし依然として容器選択性は通常のチューブサンプルと同様というわけではありません。また、二次元バーコードを刻印するという付加価値の対価として、チューブ単体の価格も幾分高価であることも課題の一つです。
RFIDを用いた非接触識別

RFIDは、Radio Frequency IDentifierの頭文字を取ったもので、情報を保持したタグ(ICチップ)から、電磁界や電波による近距離の無線通信を用いて情報をやりとりする技術の総称です。近年では、アパレル・物流業界を主に普及が進んでおり、次世代の自動認識分野を支えるコアテクノロジーになりつつあります。
いままで検体の識別は、見通し状態でバーコード読取するしかありませんでした。RFIDを使えば、検体がケースや箱に入った隠ぺい状態であっても、電波・磁界を用いて非接触で、複数の検体を一括で識別することができます。
検体の識別を極めて短時間で行えるため、温度感受性の高い細胞や血液、組織といった生体サンプルへの常温への暴露リスクを最小限に留めることができ、一連処理のスループット向上にも繋がります。
また、RFIDタグを包埋したラベルソリューションでは、今までの識別ラベルを用いた検体管理の拡張として運用できるため、全体のワークフローや作業手順書(SOP: Standard Operation Procedure)を大きく変更することなく導入できるのもメリットの一つと言えるでしょう。
デメリット
近年、経済産業省のRFID利用の推進などが積極的に行われ、知名度の向上とサプライチェーンへの普及が進みつつありますが、依然として課題となるのはRFIDタグの価格です。価格は下がりつつありますが、識別ラベルに包埋するなどの追加処理からコスト上昇は避けられず、普及の課題のひとつとなっています。
RFIDは、電磁界・電波を使いタグとの通信を行います。RFIDタグは、電波の到達距離(=読取距離)や識別する対象物の形状、サイズ、内容物によりその特性を考慮した様々な種類があります。

バイオ・ライフサイエンス分野で使用される検体は、クライオチューブやバイアルなど、非常に小さなものが多く、適切なRFIDタグの選択肢が限られます。また、その多くは-20~-196℃といった超低温環境で保管されるため、温度耐性、超低温での読取性能など、選定において乗り越えなければならない課題があります。
また、永続的にデータを保持できるRFIDタグも、電子部品であるため100%永久的な保証ができないといった問題もあります。
解決策
弊社では数年にわたり、これらの課題の解決に取り組んできました。
市場からもっとも最適なRFIDタグをスクリーニングしたうえで、実際に-液体窒素液相温度(196℃)にて3年以上に渡りサンプルを保管し、定期的にサンプルを取出し全数試験を繰り返してきました。
結果、高い耐久性と読取性能を保証できるRFIDタグ包埋ラベルと、一括で100本のサンプルを自動認識できるリーダーの開発に成功し、現在実採用・運用が進んでいます。
RFIDタグのデータ完全性問題については、ラベルに二次元バーコードを印字することで、データの冗長性を確保しています。万が一RFIDタグ内のデータが欠損あるいは故障した場合でも、従来のバーコード識別にてデータの保全を図ることができるのです。

まとめ
検体の識別手段には正解はありません。管理・運用する検体の種類や用途によって、適切な方法を選択すべきであり、このことが検体管理を主軸とした各種業務の効率性と完全性の手助けとなるはずです。
コスト面では、初期投資が少なくて済む識別ラベルに軍配が上がるでしょう。しかし、運用面での効率化や確実性、検体の品質維持の観点から、総合的に判断をするべきです。
弊社では長い経験と実績、技術でお客様のフレームワーク構築のお手伝いをいたします。ぜひ何でもお気軽にご相談ください。